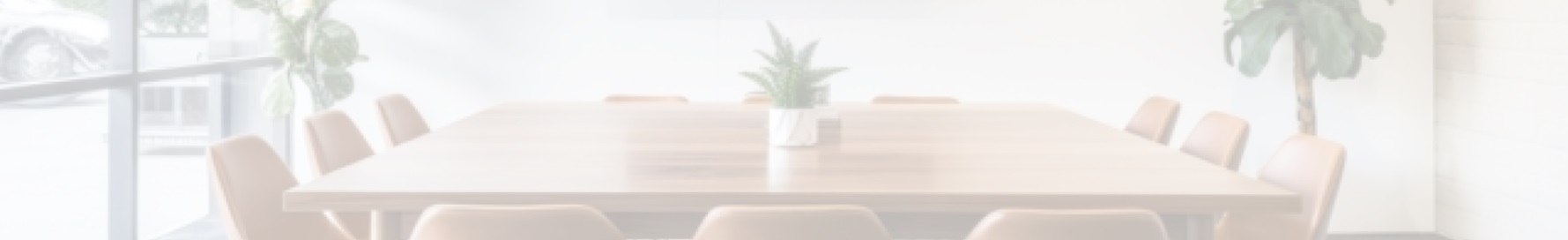【事務所ブログ】2025年☆第22回☆「家族信託をするべき事例④~二次相続に備えた柔軟な資産承継~
こんにちは、司法書士の近藤です。
学校はそろそろ夏休みに入る時期ですね。
夏休みといえば、やっぱり宿題。
私自身は、ついつい後回しにしてしまい、最後になってお尻に火がついて慌てるタイプでした。
これは認知症対策にも通じるところがあります。
余裕のあるうちに、計画的に備えておくことが大切ですね。
「家族信託をするべき事例」シリーズ、第4回は「二次相続に備えた柔軟な資産承継」をテーマにお届けします。
【事例】
豊田市にお住まいのKさん(75歳)は、数年前に奥様を亡くされ、一人息子のLさん(45歳)と同居しています。Kさんには不動産や預貯金などの資産があり、自分が亡くなったときにはすべてLさんが相続する予定です。ただ、Lさんには配偶者や子どもがおらず、将来的にLさんが亡くなった際の資産の行き先が不透明なことを懸念されていました。
Kさんは、自分が築いた財産が、できれば家族や縁ある人のために生かされてほしいとの思いを持ち、当事務所へご相談に来られました。
【解説】
通常の遺言では、自分の死後の一次相続までは指示できますが、その先の二次相続では基本的に指定することができません。そのため、LさんがKさんの財産を相続した後、Lさん自身の遺言がなければ、Lさんの死後に思わぬ第三者が財産を相続する可能性もあります。
このような場合に有効なのが、家族信託です。Kさんは、自身の不動産と金融資産を信託財産とし、Kさん自身を「委託者兼第一次受益者」、Lさんを「第二受益者」、そしてKさんの甥であるMさんを「第三受益者」に指定しました。受託者には信頼できる親族Nさんを選任しました。
これにより、Kさんが存命中は自身の生活資金として財産を使用し、Kさん亡き後はLさんの生活支援に充てられます。そして、Lさんが亡くなった際には、あらかじめ定めていたMさんが残余財産を承継するという流れが契約上明確に定められました。
このように、家族信託を活用すれば、通常の相続制度では困難な「資産の承継順序」を契約で自由に設計することができます。
【まとめ】
「自分の財産を、できるだけ望ましい形で次世代、さらにはその次の世代へと受け継いでいきたい」——そのような思いを形にできるのが、家族信託の大きな魅力です。
二次相続対策や、相続後の資産の行き先について不安がある方は、ぜひ一度、家族信託による承継設計をご検討ください。当事務所では、皆さまの想いに寄り添ったサポートをさせていただきます。
-----------------------------------------------------------------------
当事務所では、家族信託・相続・遺言に関するご相談を
「初回無料」で受け付けております。
どうぞお気軽にお問い合わせください!
-----------------------------------------------------------------------
お知らせの最新記事