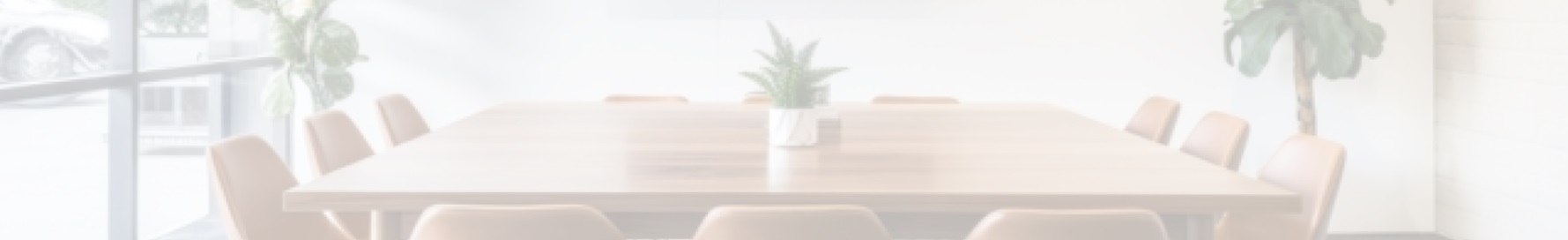【事務所ブログ】2025年☆第21回☆「家族信託をするべき事例③~共有不動産に関するトラブルを防ぐための家族信託~
こんにちは、司法書士の近藤です。
ヨーロッパでは熱波が深刻で、スペインではなんと46度を記録したそうです。ここまで気温が上がると、外出するのも危険ですね。
私が子どもの頃は、夏でも涼しさを感じる日がありましたが、今ではすっかり「酷暑」が当たり前になってしまった気がします。
さて、「家族信託をするべき事例」シリーズ第3回は、「共有不動産に関するトラブルを防ぐための家族信託」をテーマにご紹介します。
【事例】
豊田市内に不動産を持つAさん(80歳)は、妻に先立たれた後、長男と長女の二人の子どもに相続させるつもりで自宅の名義変更を検討していました。しかし、将来的にその不動産が共有状態になると、売却や管理に関して意見が合わずトラブルになるのではと懸念され、当事務所にご相談にいらっしゃいました。 【解説】
相続によって不動産を兄弟姉妹で共有することになると、将来的に売却・修繕・建替えなどの場面で意思決定が難しくなるケースが多く見られます。共有者の1人でも反対すれば、不動産の有効活用ができなくなるというリスクがあるためです。
このような場合、家族信託を活用して、不動産の管理・運用を特定の人に託すという方法があります。今回のEさんのケースでは、
・自宅不動産を信託財産とし、Aさんを「委託者兼受益者」、長男を「受託者」として、信託契約を締結しました。
・Aさんの死後は、長男が受託者として不動産の売却や賃貸を判断・実行できるようにし、得られた収益を相続人である長男・長女に分配する仕組みとしました。
これにより、不動産の共有状態を避けつつ、円満な相続と資産活用ができる体制を整えることができました。
【まとめ】
相続後に不動産が共有となることで生じるトラブルは少なくありません。あらかじめ家族信託を活用することで、意思決定をスムーズにし、家族間のトラブルを回避することができます。
不動産を所有されている方は、将来の管理や相続の方法について、ぜひ一度ご検討ください。当事務所では、状況に応じた最適なご提案をさせていただきます。
-----------------------------------------------------------------------
当事務所では、家族信託・相続・遺言に関するご相談を
「初回無料」で受け付けております。
どうぞお気軽にお問い合わせください!
-----------------------------------------------------------------------
お知らせの最新記事