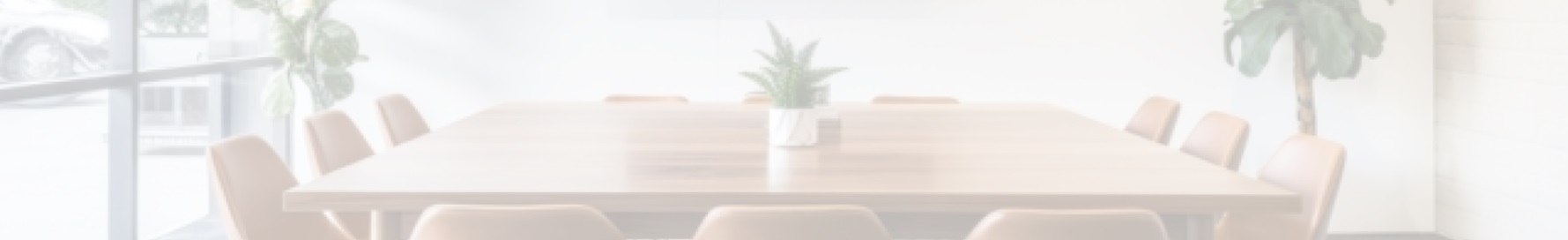【事務所ブログ】2025年☆第13回☆「遺言を残すべき事例④:再婚した家庭のケース」
みなさん、こんにちは。
春の暖かさとともに、新しい生活が始まった方も多いのではないでしょうか。
さて、「遺言を残すべき事例」シリーズの第4回は、
「再婚家庭のケース」についてお話しします。
再婚家庭では、前の配偶者との子ども(連れ子)や、
現配偶者との間に子どもがいないといった事情が絡むため、相続が複雑化しやすいのが特徴です。
1. 再婚家庭の相続、意外と“もめやすい”?
再婚したご夫婦で、配偶者に連れ子がいる、または自分の子どもと血縁がないという場合、
「誰が相続人になるのか」がわかりにくく、話がこじれやすくなります。
例えば…
•前妻との子どもと、今の奥さんがまったく面識がない
•夫が亡くなった後、奥さんと前妻の子どもが対立
•夫の実子が、「母親じゃない人に財産を渡したくない」と反発
こうした状況では、感情的なもつれが発生しやすく、
「相続争い(=争族)」につながるリスクが非常に高くなります。
2. 再婚家庭にこそ、遺言が必要な理由
再婚家庭では、遺言があるかないかで、相続の行方が大きく変わります。
特に以下のような意向がある場合には、遺言が不可欠です。
•「今の妻にきちんと財産を遺したい」
•「前の結婚での子どもたちとも、円満に整理しておきたい」
•「血縁のない連れ子にも財産を遺したい」※遺言がないと相続できません
【遺言の具体例】
遺言書
私は、下記のとおり遺言する。
1.妻 ○○(生年月日:昭和○年○月○日)に、私の自宅不動産を相続させる。
2.長女 ○○(前妻との子)に、預貯金のうち500万円を相続させる。
3.次女 ○○(現妻の連れ子)に、現金300万円を遺贈する。
令和○年○月○日
(署名・押印)
※連れ子に財産を渡す場合は、「相続」ではなく「遺贈」として記載する必要があります。
3. 法定相続では“気持ち”が伝わらない
法定相続だけに頼ると、血縁関係に基づいて自動的に財産が分配されます。
ですが、再婚家庭ではそれがトラブルの種になることも少なくありません。
•「こんなにお世話になった妻が、家を失ってしまった」
•「親から何も聞いていなかったのに、突然相続の話がきた」
•「連れ子だけが何ももらえないのは不公平では?」
このような“感情のズレ”を防ぐには、
ご本人の意思を明確に示す「遺言」がとても有効です。
まとめ
✔ 再婚家庭では、相続関係が複雑になりやすい
✔ 血縁のない配偶者の子には、遺言がなければ財産は渡らない
✔ 家族の気持ちのすれ違いを防ぐには、遺言が一番の備え
「誰に、何を、どれだけ渡したいか」
それを明確に残すことが、ご家族への最大の思いやりです。
再婚家庭に限らず、相続で心配なことがあれば、いつでもお気軽にご相談ください。
お知らせの最新記事