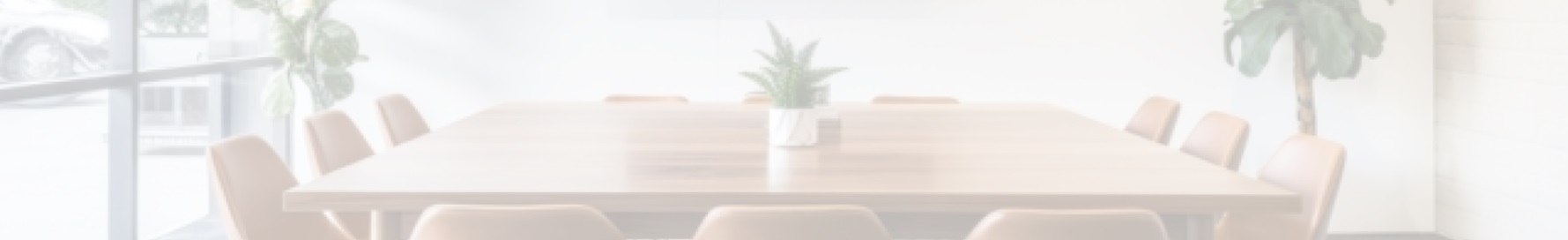【事務所ブログ】2025年☆第8回☆「家族信託における問題点と対処方法-その3-」
みなさん、こんにちは。
新潟をはじめ、各地で大雪が降っているようです。私も時折、北陸地方の公証役場へ出張することがあり、現地の皆さまのことを案じておりました。
さて、先週に引き続き、「家族信託における4つの問題点」について、本日は、次の問題点とその対処方法について解説します(順番が前後してしまいすみません)。
「家族信託は財産管理に特化しており、成年後見のように身上保護に関する契約代理ができない。」
________________________________________
身上保護に関する契約とは?
身上保護に関する契約とは、以下のようなものを指します。
•介護サービスの利用契約
•介護施設などへの入退所契約
•医療機関での治療や入院に関する契約
本人が認知症などにより判断能力を失うと、これらの契約を自分で行うことができなくなります。そのため、代わりに契約を結べる人(後見人)を裁判所に選任してもらう必要があります。これが法定後見制度です。
________________________________________
法定後見のリスク
法定後見人は裁判所が選任するため、必ずしも家族が選ばれるとは限りません。
見ず知らずの弁護士や司法書士などの専門職が後見人になることも多々あります。
せっかく家族信託を利用して財産管理の準備をしても、結果的に法定後見人が財産管理を担うことになりかねません。
________________________________________
対処方法:「任意後見契約」の活用
そこで、信託契約とあわせて「任意後見契約」を締結することをおすすめします。
「任意後見契約」とは、本人の判断能力が低下した場合に備えて、事前に後見人を決めておく契約です。
これにより、万が一認知症になった場合でも、あらかじめ指定した親族などが後見人となり、信託契約の趣旨を尊重しながら、財産管理以外の契約代理も担うことができます。
________________________________________
ご相談はお気軽に!
当事務所では、家族信託・相続・遺言に関するご相談を初回無料で受け付けております。
どうぞお気軽にお問い合わせください!
________________________________________
お知らせの最新記事