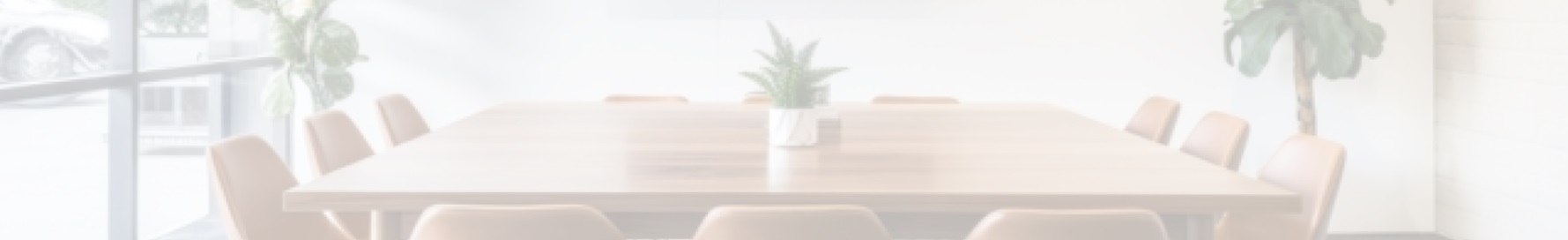【事務所ブログ】2025年☆第6回☆「家族信託における問題点と対処方法-その1-」
みなさん、こんにちは!
寒かった2月が終わり、3月がスタートしました。
だいぶ暖かくなり、いよいよ春の気配を感じる季節になってきましたね。
さて、前回から「家族信託における4つの問題点」への対処方法をご説明していますが、
本日は次の問題点とその対処方法について解説します。
「家族信託は、信託されていない財産には効力が及びません。」
-----------------------------------------------------------------------
信託できる財産とは?
-----------------------------------------------------------------------
信託財産とするためには、
「財産的な価値があり、かつ、移転や処分が可能であること」が必要です。
具体的には以下のとおりです。
1. 現金
銀行預金や現金など。
2. 有価証券
株式、債券、投資信託など。
3. 不動産
土地、建物、マンションなど。
4. 動産
自動車、貴金属、美術品など。
5. 知的財産権
特許権、著作権、商標権など。
6. 債権
貸付金、売掛金など。
7. その他
信託受益権、ゴルフ会員権など。
-----------------------------------------------------------------------
信託できない財産とは?
-----------------------------------------------------------------------
1. 借金や保証債務
2. 個人の一身専属権
→ 年金受給権、扶養請求権など。
※ただし、年金が振り込まれた預貯金を現金として信託することは可能です。
3. 預貯金債権(譲渡禁止特約があるもの)
→ 通常、金融機関の預貯金債権には譲渡禁止特約が付されているため、
預貯金そのものを信託することはできません。現金として信託することになります。
-----------------------------------------------------------------------
信託されていない財産は遺産分割の対象となる
-----------------------------------------------------------------------
自益信託で、かつ受益者である本人が亡くなった場合、
信託されている財産は契約で定めた帰属権利者に移転します。
これを「信託の遺言機能」と言います。
一方、信託財産となっていない受益者個人の財産は、
この対象とはなりません。
例えば、年金受給権そのものは信託できないため、
2ヶ月に一度振り込まれる年金は信託財産とはならず、
本人が認知症等になると凍結され、亡くなると遺産分割の対象となります。
財産凍結を避けるためには、
なるべく本人の預貯金に残高を残さないように、
定期的に追加信託を行うことが重要です。
また、「遺産分割を避けるためには」
家族信託とは別に遺言を作成する必要があります。
-----------------------------------------------------------------------
ご相談はお気軽に!
当事務所では、家族信託・相続・遺言に関するご相談を
「初回無料」で受け付けております。
どうぞお気軽にお問い合わせください!
-----------------------------------------------------------------------
お知らせの最新記事