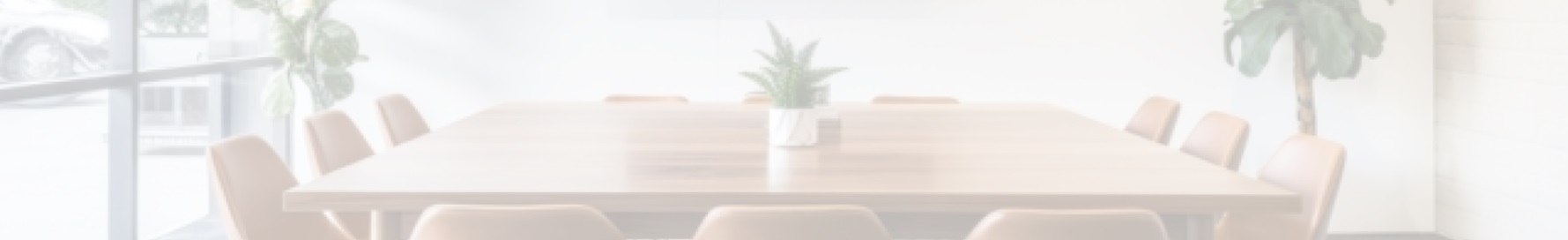遺言執行者を専門家に依頼すべき理由
みなさんこんにちは。
司法書士の近藤です。
本日は、遺言執行者を誰にするべきかについてです。
まず、前提として、遺言執行者そのものを遺言で指定すべきかについてですが、結論から申し上げると、指定しておくべきだと言えます。
遺言執行者がいない場合、相続人全員が協力しなければ手続きがとれないものもあり、遺産をもらえない相続人と感情的な対立が生じて協力が得られず、執行業務が進まなくなるおそれもあります。
次に、遺言執行者は受贈者(財産をもらう人)でもなることができるため、受贈者を遺言執行者とするケースが多く見られますが、一般の方を執行者にすると、次のような不都合が生じる可能性があります。
1、受贈者が遺言執行者となる場合、遺産をもらえない相続人などから、受贈者が遺産を独り占めしようとしているのでないかとあらぬ疑いをかけられ、無用なトラブルを招くおそれがある。
→中立公正な第三者である専門家が、遺言執行者として関与することにより、非受益相続人の反感に対する抑止力となり、トラブル防止につながる。
2、法的知識のない一般の方にとって、執行業務は決してたやすいものではなく、大きな心理的負担が生じる。例えば、改正により、遺言執行者による就任時における相続人への遺言内容を通知する義務が明文化されたため、通知しないと明らかな法律違反となる(これまで、一般の方が遺言執行者となる場合、あえて通知しないようなケースが多く見られたようである。)。
→法律の専門家が執行者となることで、大きなストレスを感じることなく、安心かつ確実に遺言の内容を実現することができる。
3、改正により、「相続させる」という文言で相続人にさせた場合、法定相続分を超える部分については、登記をしなければ、第三者に対抗できなくなった。例えば、債権者から差押えがされた場合、登記をしておかなければ、法定相続分を超える部分については権利を主張できなくなってしまう。
→法律の専門家であり、かつ、登記に精通している司法書士などが執行者となり、迅速に登記をすることで、確実に権利の保全を図ることができる。
特に相続法の改正で、遺言執行者の業務については、より高度な法律知識が必要になったと言えます。これからは、司法書士や弁護士などの専門家を遺言執行者にしておくのが無難でしょう。
なお、改正相続法の施行期日は、下記のとおりとなります。
1、原則的な施行期日
→2019年7月1日
2、自筆証書遺言の方式緩和(財産目録について自書不要)
→2019年1月13日
3、配偶者居住権および配偶者短期居住権の新設等
→2020年4月1日
近藤
お知らせの最新記事
-
2026.01.05
2026年☆第29回☆「事務所ブログ」を更新しました!
-
2025.12.18
年末年始休業のご案内