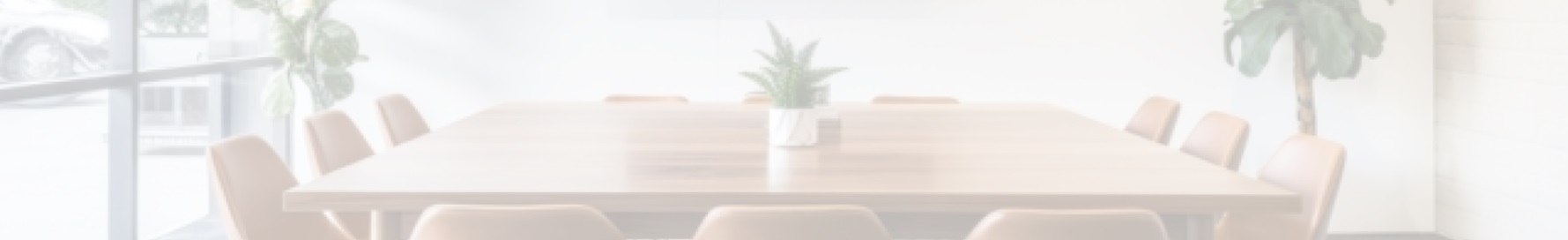相続法が変わります⑦~相続の対抗要件に関する見直し~
みなさんこんにちは。
司法書士の近藤です。
前回は、相続法改正のうち、「遺留分の対象となる相続人に対する生前贈与の範囲が変更される」についてでした。
本日は、少し専門的な話となりますが、「相続の対抗要件に関する見直し」についてです。
これまで、「相続させる」という文言で相続人にさせた場合、法定相続分を超える財産であっても、対抗要件を備えることなく第三者に対抗できましたが、これが改正によってできなくなりました。
したがって、今後は、迅速に登記をすることが重要となります。
あわせて、遺言執行者の権限に関して、相続を原因とする登記は、相続人からの単独申請でできる関係から、遺言執行者にはは申請権限がないとされていたところ、改正民法1014条2項で、遺言執行者にも権限が与えられることになりました。
【参考判例】 最判平成14年6月10日
特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」趣旨の遺言は,特段の事情のな
い限り,何らの行為を要せずに,被相続人の死亡の時に直ちに当該遺産が当該相続
人に相続により承継される(最高裁平成元年(オ)第174号同3年4月19日第
二小法廷判決・民集45巻4号477頁参照)。このように,「相続させる」趣旨
の遺言による権利の移転は,法定相続分又は指定相続分の相続の場合と本質におい
て異なるところはない。そして,法定相続分又は指定相続分の相続による不動産の
権利の取得については,登記なくしてその権利を第三者に対抗することができる。
【改正・条文】
(共同相続における権利の承継の対抗要件)
第899条の2
1 相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、次条及び第901条の規定により算定した相続分を超える部分については、登記、登録その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができない。
(特定財産に関する遺言の執行)
第1014条
1(略)
2 遺産の分割の方法の指定として遺産に属する特定の財産を共同相続人の一人又は数人に承継させる旨の遺言(以下「特定財産承継遺言」という。)があったときは、遺言執行者は、当該共同相続人が第899条の2第1項に規定する対抗要件を備えるために必要な行為をすることができる。
3 前項の財産が預貯金債権である場合には、遺言執行者は、同項に規定する行為のほか、その預金又は貯金の払戻しの請求及びその預金又は貯金に係る契約の解約の申入れをすることができる。ただし、解約の申入れについては、その預貯金債権の全部が特定財産承継遺言の目的である場合に限る。
4 前二項の規定にかかわらず、被相続人が遺言で別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
豊田市・岡崎市・西三河地域で、相続でお悩みの方、ぜひ一度、当事務所までご相談ください。 当事務所では、初回相談は無料とさせていただきます。お気軽にご相談ください。
お知らせの最新記事
-
2025.12.01
2025年☆第28回☆「事務所ブログ」を更新しました!
-
2025.11.04
2025年☆第27回☆「事務所ブログ」を更新しました!
-
2025.09.03
「家族信託・相続・遺言の基本と対策セミナー」を開催しました。