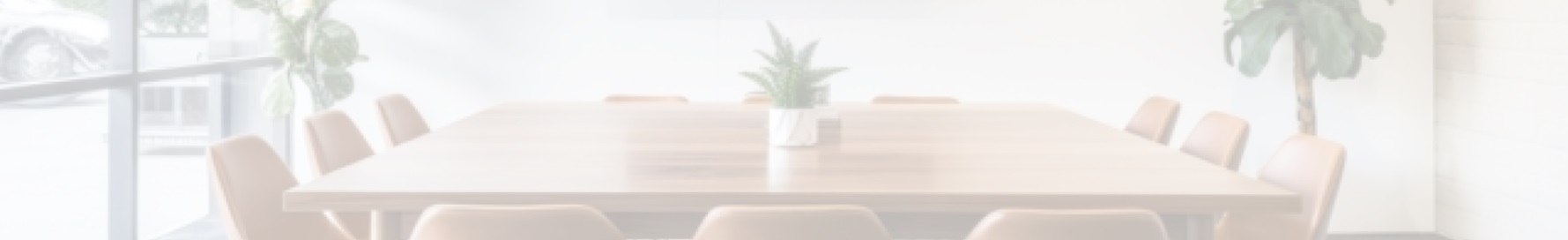相続法が変わります⑥~遺留分の対象となる相続人に対する生前贈与の範囲が変更~
みなさんこんにちは。
司法書士の近藤です。
前回は、相続法改正のうち、「特別寄与料」についてでした。
今回は、遺留分の対象となる相続人に対する生前贈与の範囲が変更されることについてでです。
これまで、相続人に対する生前贈与(特別受益に該当するもの)は、原則として年数に関係なく、遺留分減殺請求の対象となっていました(最高裁平成10年3月24日第三小法廷判決)。
今回の改正により、相続人に対する生前贈与(特別受益に該当するもの)については、相続開始前の10年間にしたものに限り、遺留分減殺請求の対象となります。
ただし、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与(特別受益に該当するもの)したときは、10年前より前にしたものについても対象となります。
ちなみに、「損害を加えることを知って」とは、「加害の目的」まで必要ではなく、「加害の認識」で足り(大審院判決)、具体的には、「損害となりうる事実」を知っていれば、法律の知不知や、誰が遺留分権利者であるかの認識も不要とのこと。
どの程度の事実の認識が必要かについては、
・贈与財産の全財産に占める割合
・贈与の時期
・贈与者の年齢
・健康状態
・職業などから将来財産が増加する可能性の有無
以上から、どの程度の贈与をなしたら遺留分を侵害するかといえるかの総合判断となるそうです。
【判例要旨】
平成10年3月24日最高裁判所第三小法廷判決
民法九〇三条一項の定める相続人に対する贈与は、右贈与が相続開始よりも相当以前にされたものであって、その後の時の経過に伴う社会経済事情や相続人など関係人の個人的事情の変化をも考慮するとき、減殺請求を認めることが右相続人に酷であるなどの特段の事情のない限り、同法一〇三〇条の定める要件を満たさないものであっても、遺留分減殺の対象となる。
【現行条文】
第1030条 贈与は、相続開始前の一年間にしたものに限り、前条の規定によりその価額を算入する。当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、一年前の日より前にしたものについても、同様とする。
【改正条文】
豊田市・岡崎市・西三河地域で、相続でお悩みの方、ぜひ一度、当事務所までご相談ください。 当事務所では、初回相談は無料とさせていただきます。お気軽にご相談ください。
お知らせの最新記事
-
2025.12.18
年末年始休業のご案内
-
2025.12.01
2025年☆第28回☆「事務所ブログ」を更新しました!
-
2025.11.04
2025年☆第27回☆「事務所ブログ」を更新しました!