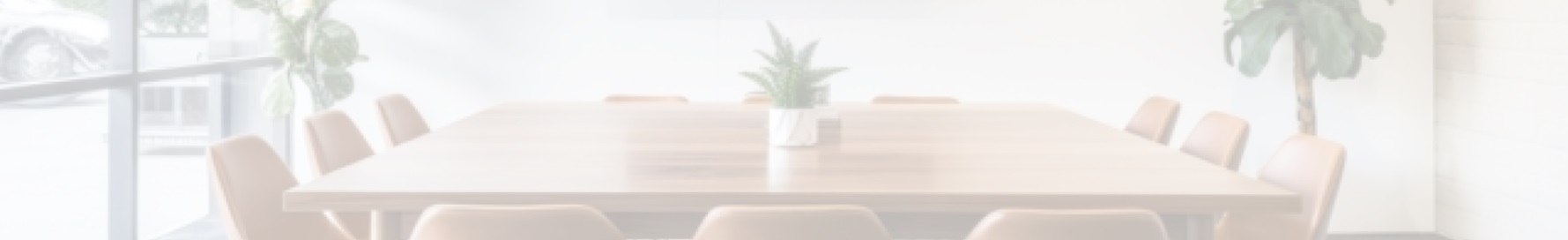相続法が変わります②~自筆証書遺言の保管が法務局で可能に~
みなさんこんばんは。
司法書士の近藤です。
さて、今回も相続法改正についてです。
前回は、自筆証書遺言における財産目録が自書不要についてでしたが、
今回は、「自筆証書遺言が法務局で保管」についてです。
改正の主な内容は下記のとおりです。
1、遺言書の保管の申請
- 遺言書の保管の申請は,遺言者の住所地若しくは本籍地又は遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する遺言書保管所の遺言書保管官に対してすることができます(第4条第3項)。
- 2、遺言者による遺言書の閲覧,保管の申請の撤回
- 遺言者は,保管されている遺言書について,その閲覧を請求することができ,また,遺言書の保管の申請を撤回することができます(第6条,第8条)。遺言者の生存中は,遺言者以外の方は,遺言書の閲覧等を行うことはできません。
- 3、遺言書の保管の有無の照会及び相続人等による証明書の請求等
- 特定の死亡している者について,自己(請求者)が相続人,受遺者等となっている遺言書(関係遺言書)が遺言書保管所に保管されているかどうかを証明した書面(遺言書保管事実証明書)の交付を請求することができます(第10条)。
- 遺言者の相続人,受遺者等は,遺言者の死亡後,遺言書の画像情報等を用いた証明書(遺言書情報証明書)の交付請求及び遺言書原本の閲覧請求をすることができます(第9条)。この場合、遺言書保管官は,速やかに,当該遺言書を保管している旨を遺言者の相続人,受遺者及び遺言執行者に通知します(第9条第5項)。
- 4、遺言書の検認の適用除外
- 遺言書保管所に保管されている遺言書については, 遺言書の検認(民法第1004条第1項)は不要です(第11条)。
- 5、手数料
- 遺言書の保管の申請,遺言書の閲覧請求,遺言書情報証明書又は遺言書保管事実証明書の交付の請求をするには,手数料を納める必要があります。(第12条)
- 以上、あくまで遺言書の「保管」に関する改正であり、その限りでは公正証書遺言に類似しますが、
遺言内容には法務局が関わらないという点に大きな違いがあります。
したがって、「争族」にならないような遺言書を作るには、公証人や司法書士などの専門家のアドバイスを通して、公正証書遺言にしておくのも一つでしょう。
この改正については、平成32年7月13日までに施行予定です。
近藤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
豊田市・岡崎市・西三河地域で、相続でお悩みの方、ぜひ一度、当事務所までご相談ください。 当事務所では、初回相談は無料とさせていただきます。お気軽にご相談ください。
豊田市・岡崎市・西三河地域で、相続でお悩みの方、ぜひ一度、当事務所までご相談ください。 当事務所では、初回相談は無料とさせていただきます。お気軽にご相談ください。
お知らせの最新記事
-
2025.12.01
2025年☆第28回☆「事務所ブログ」を更新しました!
-
2025.11.04
2025年☆第27回☆「事務所ブログ」を更新しました!
-
2025.09.03
「家族信託・相続・遺言の基本と対策セミナー」を開催しました。