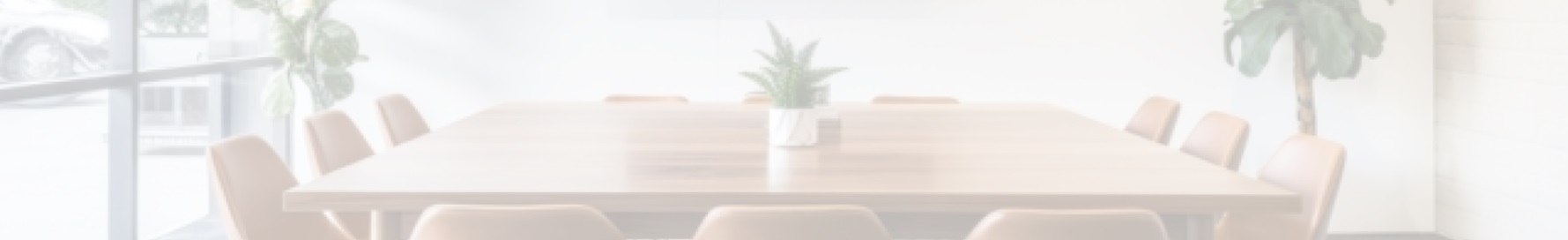【事務所ブログ】2025年☆第19回☆「家族信託をするべき事例①~認知症による財産凍結のリスクに備える~
こんにちは、司法書士の近藤です。
先週は梅雨の晴れ間で暑い日が続きましたが、今週は曇りの日が多く、少しだけ暑さも和らぎそうですね。
さて、近年「家族信託」という言葉を耳にする機会が増えてきたと感じている方も多いのではないでしょうか。
実際、当事務所でも家族信託に関するご相談が年々増えており、遺言や成年後見と並ぶ高齢者の財産管理の選択肢として、注目を集めています。
そこで今週から、「家族信託をするべき事例」と題して、典型的なケースを毎週ひとつずつ取り上げながら、家族信託の有効性や注意点について、わかりやすくご紹介してまいります。
第1回は、「認知症による財産凍結のリスクに備える」というテーマでお届けします。
【事例】
豊田市にお住まいのAさん(78歳)は、持ち家にお一人で暮らしており、最近少し物忘れが増えてきたことを気にされていました。
万が一、認知症を発症した場合に、介護施設への入居費用の確保や持ち家の売却手続きが自分ではできなくなることを心配され、息子さんと相談のうえ、当事務所にご来所されました。
【解説】
認知症になると、法律行為を行うための判断能力(意思能力)が失われ、預金の引き出しや不動産の売却といった手続きができなくなるおそれがあります。
その結果、施設入居費の捻出ができない、相続対策としての不動産処分が進められないなど、いわゆる財産凍結の状態に陥ってしまう可能性があります。
こうした事態を未然に防ぐ手段として、有効なのが「家族信託」です。
今回のAさんのケースでは、
自宅不動産や預貯金を信託財産とし、
Aさんが「委託者兼受益者」、息子さんを「受託者」とする。
家族信託契約を締結することで、将来Aさんの判断能力が低下した場合でも、息子さんが財産の管理や処分を代行できるように備えました。
この仕組みにより、介護施設への入居費用の確保や、必要に応じた自宅の売却も、スムーズに行える体制が整いました。
【まとめ】
「判断能力が失われる前に、備えておきたい」
そんな思いを形にできるのが、家族信託の大きな魅力です。
認知症対策としては成年後見制度もありますが、「柔軟な財産運用」や「家族による主体的な管理」ができる点で、家族信託は非常に有効な手段といえます。
ただし、家族信託は一人ひとりの状況に応じて設計するオーダーメイドの制度であるため、専門家のサポートが不可欠です。
将来への不安や準備に関心のある方は、どうぞお気軽にご相談ください。
-----------------------------------------------------------------------
当事務所では、家族信託・相続・遺言に関するご相談を
「初回無料」で受け付けております。
どうぞお気軽にお問い合わせください!
-----------------------------------------------------------------------
お知らせの最新記事