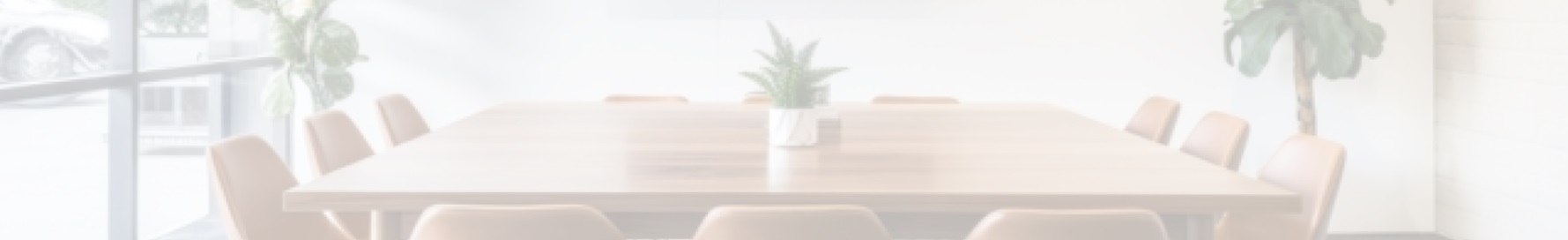【事務所ブログ】2025年☆第1回☆「家族信託」とは?
明けましておめでとうございます。
しばらくお休みさせていただいておりました事務所ブログについて、
今年から再開させていただきます。
実務における体験談など、インターネットで検索しても出てこないようなものを中心にお届けしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
今週のテーマは、
「家族信託とは?」です。
家族信託とは、契約などで決めた信託の目的(本人の福祉を確保するためなど)に従って、家族に財産を託すものであり、財産管理の手法の一つです。
財産を託す人を委託者、託された人を受託者、信託によって利益を受ける人を受益者と言います。
受託者は、信託の目的に従って、託された財産を管理などすることになります。
家族信託には様々な活用法がありますが、その一つに認知症対策としての活用法があります。
一般的に、認知症になると、銀行預金等が引き出せなかったり、不動産を売却することができなくなります。
銀行預金等については、実際のところ、普通預金であれば、家族が代わりにキャッシュカードで下せてしまいますが、使途不明金として、後々相続人間でもめる原因ともなりおすすめはできません。また、引出限度額があるため、まとまったお金を引き出すには、窓口で手続きをとる必要があります。本人が認知症である場合、預金の引き出しは拒絶され、結果として、預金が凍結されることになります。
この凍結を解除するためには、法定後見制度の手続きをとらなくてはなりません。
法定後見制度を利用するためには、家庭裁判所に後見人選任の申立てがすることになりますが、後見人を誰にするかは家庭裁判所が決める(もっとも、家族を後見人候補者にしたいという希望を出すことは可能)ところ、親族以外の第三者が選任される割合は、全体の81.9%となっております(最高裁判所成年後見関係事件の概況(令和5年1月~12月))。
後見人は、財産管理権(本人の財産を管理し、処分する権利(ただし例外あり))や身上監護権(本人の生活や健康管理に関して法律行為を行う権利)を持ち、銀行預金等はすべて後見人が管理することになります。
後見人は財産の維持、増加させることができても、合理的な理由がない限り、財産を減少させることはできませんので、親族への贈与、相続税対策などは本人の財産を減少させる行為となり原則、認められません。
また、居住用不動産(自宅、敷地など)を売却等するには、家庭裁判所の許可が必要となります。(民法第859条の3、成年被後見人の居住用不動産の処分についての許可)
なお、後見人には、一年に一回、家庭裁判所が決定した報酬が、本人の財産から支払われることになります(おおよそ、管理する財産額が1000万円~5000万円の場合。月額3万円~4万円くらい)。
このように、法定後見制度は、家族にとって負担と制約が大きい制度と言えます。
この法定後見制度に代わるものとして、家族信託が注目を集めています。
家族信託では、判断力があるうちから資産の管理や処分等を、家族に託す契約等をすることで、本人のご意向に沿う財産管理をスムーズに実行できます(そもそも、法定後見制度は本人の判断力が低下しなければ利用することができません)。
また、不動産(自宅など)の売却、相続税対策としてのアパート建築等も、受託者の責任と判断のみで可能となります。
もっとも、認知症になった後は、家族信託の契約等をすることができず、法定後見制度を利用するほかありませんので、認知症になってしまう前に、対策をしておくことが肝要です。
弊所では、家族信託、相続、遺言に関するご相談を初回無料にて受け付けております。お気軽にご相談ください。
お知らせの最新記事