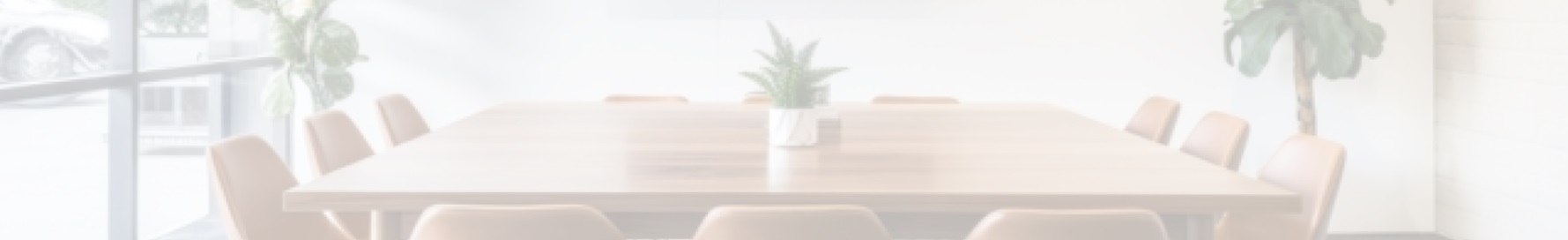民事信託の活用法①
みなさんこんにちは。
司法書士の近藤です。
さて、昨今、相続対策の一つに活用できる「民事信託」というものに注目が集まっております。
信託というと、信託銀行の「遺言信託」などの商品をイメージされる方が多いと思いますが、
これは、遺言自体の支援を行うだけ、つまり、遺言の作成、保管、実行までのサポートをするだけであり、遺言以上の何ができることはありません(遺言で法的効力が認められる事項は法律で決められています)。
一方、民事信託は遺言とは全く別の制度になります。
例えば、民事信託が当事者が内容を自由に決める「契約」であるのに、遺言は遺言者が一方的に決める「単独行為」です。また、遺言では法的効力が認められる事項が法律で決められており、自由に決められないこともあります。
平成19年の信託法大改正によって、信託の活用の可能性が大きく広がりました。
ここで、民事信託の活用法について事例を一つ挙げます。
精神障害のある子がおり、自分の死後も最後まで世話してやりたい。
遺言だと法的効力のある事項が限定されており、財産を譲り渡すことはできても、世話をするという内容まで決められない。
このようなケースでは、例えば兄弟など信頼のおける誰かを「受託者」とし財産の名義を形式上移転させ、父が当初受益者(実質的な権利を持つ人)となり、二次受益者(親の死亡後に権利を取得する人)を精神障害のある子とし、三次受益者(精神障害のある子の死亡後に権利を取得する人)を誰か希望する人に定めておくことによって、父の「子の世話をしてやりたい」というニーズに広く応えることができます。また、受託者の信頼がイマイチおけないという場合は、専門家などに「受益者代理人」として、財産の管理や執行について任せることもできます。
また、「子の世話をする」こと以外にも、父としては亡くなるまで自分の名義であり、安心して自宅に住み続けることができるますし、遺言ではないので、兄弟間の紛争になりにくい点にもメリットがあります。
民事信託には他にも様々な活用法があります。
また、相続対策の相談は無料となりますので、まずはお電話ください。
近藤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 豊田市・岡崎市・西三河地域で、相続でお悩みの方、ぜひ一度、当事務所までご相談ください。
なお、当事務所では、初回相談は無料とさせていただきます。
お知らせの最新記事
-
2026.01.05
2026年☆第29回☆「事務所ブログ」を更新しました!
-
2025.12.18
年末年始休業のご案内